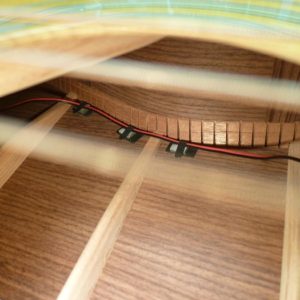ネックをリセットします。
前回とは打って変わって、全く通常通りの外し作業です。
ネックリセットも、今となっては何本やったか数える事も不可能になるほどやりましたが、そうは言っても大変な修理には変わりません。
心配性であがり症の私は、当然ながら今でも、すんごい緊張感の元、勇気を持って携わっているのです。
前回ちょっと触れた,十数年前のGuildは、まともに外す事が出来なかったですし、エクステンションが付いたJ-200 では普通に抜ける構造ではなかったり、どうがんばっても、外れない、外せない場合が何度かありましたが、そこでやめて戻すことは出来ないので、方法を変えて外す事を考えなくてはなりません。
「いい加減慣れたでしょ。」と言われれば、流石に修理屋家業ぅん十年、慣れたと言えばそうかもしれませんが、慣れてこれです。15フレットに穴を開けるときにやっと最近ドキドキしなくなったかもしれません。
人様の大事な物、本当はこんな事したくないのですが、なんで修理屋になったろうと思う時、ビビリだから丁度いいのかもしれないと思っています。
であれば、販売店や製作家になればよかったかと言えば、それはそれで苦労があるはずですから、隣の芝は青く見えるものなのでしょう。
お客様は神様では無いので、お互いが尊重しあうものだと思っていますが、ショップではお客を半神位の扱いしなければならない場合もあるでしょうし。
製作家だって、私が羨ましいと思うような人は一握りだと思いますし。
やはり落ち着くところに落ち着いているのだと思います。